『かんもく』は 病気? 障がい? 個性?
■「障がい」として受け入れてもいい

『かんもく』は、
・医学的には・・・「社会不安障がい」の一種とされています
・法令上は・・・「発達障がい者支援法」で定義される「発達障がい」に位置付けされています
・学校教育では・・・特別支援教育の対象として「情緒障がい」に分類されています
早期発見と早期の治療や適切な支援を受けることによって、『かんもく』の症状が改善されることもあります。
しかし、子どもの頃に出始めた『かんもく』が、大人になれば改善されるわけではありません。
しかし、『かんもく』の症状のみで、で身体障がい者手帳や精神障がい者手帳を受けることは難しいかもしれません。
『かんもく』の症状は、少しなら話せる、小声であれば話せる人もいれば、全く話せない、または話せないし体も動かなくなってしまう人など症状は、軽度~重度まで様々です。
しかし、『かんもく』の症状が続くことにより、「困ること」があります。
学校、職場において正しい理解と適切な支援をしてもらうために知っておいてもらううことが必要なことがあります。
医療機関、市の相談機関、市の支援教室の利用が必要なことがあります。
将来、就職に関して正しい理解と適切な支援をしてもらうために知っておいてもらううことが必要なことがあります。
『かんもく』の程度により、正確な医師の診断を受け、障がいと診断してもらうことにより、「障がい者雇用枠」として就職の支援が受けられる場合があります。
『かんもく』を正しく理解してもらうことで、適切な支援を受けながら希望の職種の選択肢が広がる可能性もあります。
学校の特別支援教室に在籍する子どももいれば、普通学級で過ごせる子どももいます。
しかし、軽度であるがゆえに静かに学習ができてしまうため、適切な支援が受けられないまま長年放置をされてしまうことがあります。
『かんもく』の子どもが、学校での社会的活動を行う場合、適切な支援は必須であると考えます。
知的障がいを伴っていない場合、普通学級で他の子ども達ど変わらずでき、「話せない」こと以外はできてしまう子どもも少なくありません。
「ちょっと背中を押してみよう」「先生がきっかけを作ってどうにかしよう」と早急に、無理な要求をされてしまうと大きな負担を感じます。
「何も言わないので、声をかけなければおとなしく聞いている」「そんなに、普通の子どもと変わらないのではないか」と判断されてしまえば、誤った指導方法により『かんもく』の症状が悪化してしますことがあります。
http://kanmoku.org/kanmokutoha.html(参考:かんもくネットより)
■「個性」でもいい
「障がい」と言われてしまうと悲観的になってしまうのであれば、「私の個性」として受け入れましょう。
『かんもく』は遺伝的要素も大きいといわれます。
きっと我が子も毎日がこんな感じなんだろう!
実際に、私には『かんもく』に近い性格的要素があります。
「大勢の人に注目される」ことによる不安感を、他の人よりも強く持ってしまう自覚があります。
しかし、「話せない」ことはありません。
大人になって始めたテニスの試合に、初めて出場しました。
体が震度6くらい震えてしまいそうな感覚とふわふわした状態で、ラケットにボールを当てるだけで精一杯でした。
楽しむことはできませんでした。
テニスは大好きで自分で試合に出たいと望んだのですが、体が思うように動かないのです。
「やりたいのにできない」「思うように自分の実力を発揮できない」悔しい気持ちでした。
今は、何度も試合に出場をして、「試合に慣れる」ことを目標にしています。
少しずつ楽しくなってきました。
でも、初めて組む相手とは3回位一緒に出場しないと味方に人見知りをしてしまいます。
対戦相手よりも一緒に組む味方に人見知りをしています。
まだまだ道のりは長い。
でも、それが「自分」なのです。
『かんもく』の我が子の生まれもった気質や性格
『かんもく』には、生まれ持った気質と性格が大きく影響していると考えられます。
「不安感が強い」「緊張しやすい」など性格的気質を持っていることが多いそうです。
「甘やかしているのでは」「育て方がいけなかったのでは」という方がいますが、基本的に育て方などの要因は関係がないとされています。
私の子どもは『かんもく』の症状があります。
赤ちゃんの頃から、とても神経質で小さな物音にもすぐに反応して起きてしまいます。
夜泣きもとてもひどく、3歳くらいまで毎日2時間おきに号泣していました。
朝起きた時から寝るまで、ちょっとしたことでかんしゃくを起こし、よく泣いていました。
生後5ヵ月の頃に、買い物の途中にすれ違いざま我が子に「わ!」という声が聞こえました。
「何だろう」と我が子を覗くと、すごい顔で通りすがりの人を睨みつけていました。
それからずっと、人の多い場所に行くと人を睨みつけていることが多いのです。
でも睨みつけていたのではないのです。
話ができるようになったの頃に、「睨んだらだめよ」というと、「睨んでない!」と言うのです。
本人は睨んでいるのでははく、ただ「緊張していただけ」だったのです。
緊張すると表情がパッと変わります。
家では見たこともないような無表情になったり、上目遣いになって睨みをきかせているような表情で相手を見てしまうことがあります。
「目力がすごいね」と仲の良いお母さん達も初めはビックリしていましたが、緊張していることを伝えると理解してくださる方もたくさんいました。
今は、友達の輪の中に入っています。
睨みつけるような表情ことは少なくなりました。
緊張すると無表情になることがあります。
学校で「話す」ことはできません。
できるようになるかもしれないし、できないままかもしれません。
でも、友達の輪の中で笑顔で参加して楽しく学校生活を送っています。
「そのままの自分」を受け入れよう

「障がい」でも「個性」でも「私」は「私」
「そのままの自分」とこれからもずっと付き合っていくのです。
そして「そのままの自分」である我が子と共に、親は生きていくのです。
大切なことは、「そのままの自分」である子どもとどう過ごしていくかを考えることです。

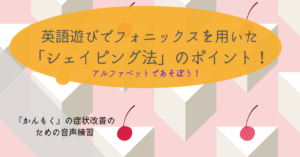


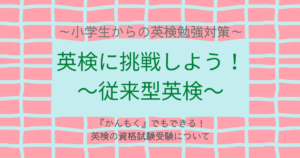




コメント